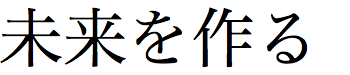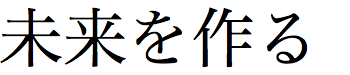
読書の記録
経営コンサルタント、税理士の人が書いた本です。
私たちは消費社会の奴隷だそうです。
映画『マトリックス』に出てくるコンピューターが養殖されてる人間と変わらないそうです。
そうなってしまっても解決策などなく、当たり前のことをやるしかないと。
当たり前のこととは支出を減らす、です。そうですかー。
以下、学んだポイント。
- リスク資産と無リスク資産の配分が大事
- 家を購入したならそれはリスク資産なので他のリスク資産の運用は考えなくてよい
日本人女性の投資家の書いた本です。
アメリカ人、中国人のお金に対する考え方が書かれています。
経済は世界中とつながっているので、考え方も変えていく必要があると思いました。
以下、学んだポイント。
- ひとつのかごに卵を全部入れるな
- リスク許容度、冷静さ、最悪のシナリオの3つの視点で自分に適した投資方法を検討
- 信用、知識、行動力が本当の豊かさへとみちびく
公認会計士・税理士の夫妻が書いた本です。
既に20代ではなくなっていますが読んでみました。
20代のうちに読んでおけばベストです。
30代、40代でも人生プランについてよく考えたことがないという人には読む価値ありです。
選択肢の幅は狭くはなっていますが軌道修正は出来るでしょう。
以下、学んだポイント。
- 出口戦略を考える3つのポイント
- 野瀬式お金4分割法(余ったお金を自動的に4つの資産に投資する)
ビジネスコンサルタントの人が書いた本です。
以前に同著者の「残念な人の英語勉強法」という本を読んだことがあり、それがよかったので
この本も読んでみることにしました。
5章が著者の失敗談と後悔の念になってしまっているのが残念でした。
以下、学んだポイント。
- ビジネスの世界では長所をさらに延ばすことが大事(短所を人並みにしても無意味)
レバレッジシリーズの時間に関する本です。
これは始めて知ったというような手法はなかったのですが
読みやすい文章でひとまとめになっているので、読み返したくなったときのために
手元に置いておこうと思いました。
以下、学んだポイント。
- お金を払って買った雑誌だからといって全てを読まない
- ライフワークバランスとは効率的に成果を出し、そこから生まれる時間によってプライベートを充実させるもの
赤字の事業部を建て直すというストーリー仕立ての経営の本です。
経営コンサルをやってた人が書いた本で、物語は実話を基にしているだけあって
とてもリアリティがあります。まるで自分の会社の様です。
もし、私が社長なら社員全員にこの本を配ります。
公認会計士、税理士の人が書いた本です。
銀行員を辞めてレストランを開業した男と大小売りチェーンの会長の会話形式で
経営について学べるようになってます。
とても読みやすく最後まですらすら読めてしまいました。
以下、学んだポイント。
- ドラッカーの本を読むべし
- 「マネジメント」
- 「現代の経営」
- 「創造する経営者」
- 「すでに起こった未来」
- 「明日を支配するもの」
- 「ネクスト•ソサエティ」
弁護士の人が書いた本です。謎だらけの意味は、算出の方法を
学校や会社でもきちんと教えたり説明していないから知らないままになっているということだと思います。
本当に日本のこれまでの政府は国民の暮らしをよくしようとは
微塵も考えていないのではないかと思ってしまいます。
以下、学んだポイント。
- 社員旅行も条件により課税される
- 社員販売も価格が7割未満では課税される
- 組合費も課税される
- 派遣会社に支払う派遣料は仕入れとなり、会社の消費税負担は軽くなる
120528 アイデアのつくり方を「仕組み化」する /ポール•バーチ、ブライアン•クレッグ 泉本行志=訳/ディスカバー•トゥエンティワン
/ポール•バーチ、ブライアン•クレッグ 泉本行志=訳/ディスカバー•トゥエンティワン
思考が凝り固まっている私には、役に立つテクニックがいっぱいでした。
読んでよかったです。
固定概念、既にある経験や知識、真面目さ等が創造性を妨げるそうです。
以下、学んだポイント。
- ルート探査→構築→確認→実行
- 通常の使い道とそれ以外の使い道は?
- 前提を無視する
- 別のものに見立てる
税理士の人が書いた本。
法人税にかかわるエピソードの後、それに関係する計算方法等の説明がある構成が全部で13章です。
エピソードのところはスラスラ読めて、本題のところは難しく不思議な本でした。
とにかく、法人税について理解を深めることが出来ました。
以下、学んだポイント。
- 効果的な節税プランなどない
- ケイマン諸島は法人税がゼロ
- 手許資金ではなく所得に貸されるので資金繰りに困る
- 圧縮記帳は課税の繰り延べにはなる
財務戦略コンサルタントの人が書いた本。
会計と財務の違いがなんとなくわかりました。
タイトルどおりざっくりわかりました。
ざっくりなので、もう少し自分で噛み砕いて理解する必要があります。
社長はこういうことまで考えないといけないのですね。なかなか大変です。
以下、学んだポイント。
- WACC<-会社が投資家(株主、債権者)からいくらで資金を調達しているかを表した数字(加重平均資本コスト)
- ROIC<-投下資本利益率(税引後営業利益/投下資本)
- EVA<-どれだけ企業価値が増加したか (投下資本×(ROIC-WACC))
- お金の将来価値(FV)、現在価値(PV)の考え方
- 企業、プロジェクトの価値と投資判断基準(NPV法, IRR法, 回収期間法)
- IRのミッションはWACCを下げること
- 負債もある程度は必要<-最適資本構成がある
税金というより経済の教科書でした。
日本の借金は900兆円を超えていて、国民一人あたり700万円になるそうです。
自分の寿命が来る前には破綻するのではないかと思いました。
以下、学んだポイント。
- マクロ経済→一国の経済活動全体を考える
- ミクロ経済→個々の家計や企業の経済活動を考える
- 世界の経済は「大きな政府」と「小さな政府」を30年単位で行ったり来たりしている
経営コンサルタントの人が書いた本。
様々な取引があったときに、財務諸表の数字は具体的にどう変化するかが解説されていてよかったです。
また、私にとって謎だった「のれん」の意味がやっとわかりました。
家屋の軒先に垂らす日よけの布があんなに高額な訳がないですね。
以下、学んだポイント。
- 自分の会社を設立したら、または設立しようと考えているなら財務3表を作り、シミュレーションすること
- 人間のノウハウ、特許などの知的財産は財務諸表には表れない
- キャッシュフロー計算書を見れば8パターンに分類出来て会社の状況/戦略がわかる
- 法人税率を計算するための課税所得は税引前当期純利益ではない
経営コンサルタント/株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役という肩書きの人が書いた本。
私はこの年になってようやく貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書がどういうものが理解することができました。
財務諸表の中の数字を足したり引いたり割ったりした値の意味が、その会社の何を表しているかが
たくさん説明してあって面白いと感じながら読み切ることが出来ました。
以下、学んだポイント。
- 財務諸表のチェックの順序 手元流動性→当座比率→流動比率→自己資本比率
- 損益計算書の売上高を見るときにはたな卸し資産が増えていないかも見る
- マクロ経済の動向も認識しておく
- キャッシュフローの実力値=当期純利益+減価償却費
- DCF法、EBITDA法、5倍なら買収に前向き、7~8倍は高い感じ
MBAの人が書いた本。株式と投資信託への投資を勧めていました。
長期的には株価はあがっていくので積立投資をしろ、と述べているが本当なのでしょうか。
私には株価の定価と原価の説明が役に立ちました。
以下、学んだポイント。
- 出資するからには最低でも国債の金利+5%~20%ぐらいのリターンが見込めないとリスクに見合わない
- 原価、定価のわからないものを買うということは法外な値段で買わされる可能性が高くなる
- 株価=会社の金庫の中にあるお金+将来稼ぐお金
- BPS(Book value Per Ratio) 1株株主資本
- PBR(Price Book value Ratio) 株価純資産倍率=株価/1株株主資本 1~2が標準
脱サラして焼き鳥屋を始めた男性と税理士の会話形式で、起業のメリット等を解説しています。
ド素人の私にはわかりやすく打って付けの本でした。
以下、学んだポイント。
- 順序は個人事業主→会社設立
- 会社を作るべき規模は年間売上高が毎年1000万円超かどうか
- お金は個人、物は会社に持たせる
- 株式投資も会社で行うと、損しても黒字と相殺できる